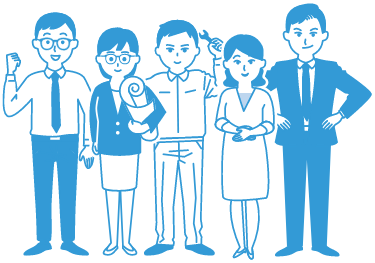未公開
万歩計に代わる次世代型の活動量測定機器。健康寿命の延長に貢献。 未公開 受賞
未公開
毎日の眠りを圧電センサーでチェック。Sleep Meter 未公開 受賞
未公開
圧電センサーで、高齢者の行動をフィードバック。安心そして一人暮らしを続ける自信へ。 未公開 受賞
未公開
塗って剥がすだけで、手軽に清掃を行える樹脂製コーティング剤 未公開
未公開
ヒートショック対策用ヒーター HEAT HEART 未公開
未公開
生涯現役社会の実現(高齢者の居場所をつくる就労システム) 未公開
未公開
簡単に探せる! 体力的に元気な「老人性認知症」の方に対する提案 未公開
未公開
アンダー・ザ・ドーム 〜自分だけの快適な寝室空間を創出できる『高機能シェルター』〜 未公開